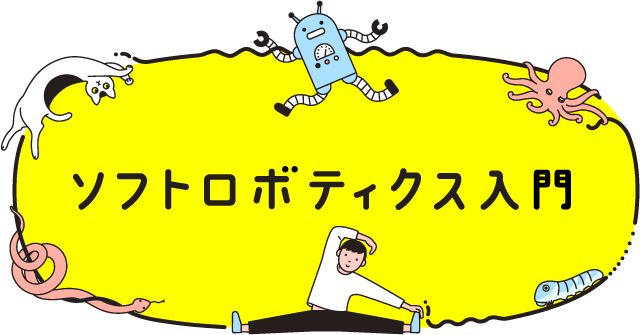黎明期
ソフトロボティクスの源流は、生物と工学の境界領域にある。
1940年代、ノーバート・ウィーナー(Norbert Wiener)は動物と機械を統一的に扱うサイバネティクス(cybernetics)を提唱し、体系化しようと試みた。1960年頃には、生物学の知見を工学に応用する学問として、医師のジャック・E・スティール(Jack E. Steele)がバイオニクス(bionics)を提案した。バイオニクスは、その後、サイボーグ技術と結びついて知られるようになる。
そのような流れの中で、二足歩行ロボットの父と言われる加藤一郎博士(1925-1994)は、独自の学問分野としてバイオメカニズム(biomechanism)を提唱した[加藤,1972]。バイオメカニズムは、生物システムの機構・機能に学ぶだけでなく、サイボーグあるいはロボットを作ることに重点を置いている。
1960年代から1970年代、早稲田大学の加藤研究室では筋肉の代わりになる動力源としてゴム人工筋が開発され、筋駆動二足歩行ロボットWAP-1が作られた。一連の研究は、後のヒューマノイドロボット開発につながっていく。
もうひとつの流れは、人間のための義肢・装具や人間型ロボットに限定せず、広く生物システムを扱う生体力学(バイオメカニクス、biomechanics)である。
梅谷陽二博士(1932-)は、機械に生物の形態・構造・機能を取り入れようとする試みについて論じている[梅谷,1970]。ここから、ヘビの生物工学的研究や、ミミズや消化器のぜん動運動の研究が発展した。東工大の梅谷研究室出身で、ヘビロボットで著名な広瀬茂男博士の著書『生物機械工学』(絶版)の副題は「やわらかいロボットの基本原理と応用」だった。
ちなみに、生物システムとは関係なく、制御の観点から柔軟構造を明示的に取り扱ったロボットシステムとしては、1980年代に研究が盛んに行われたフレキシブルアームあるいはフレキシブルマニピュレータがある。
ソフトアクチュエータ
アクチュエータは機械の動力源である。やわらかいアクチュエータのロボット応用に関して、日本で先駆的な研究が行われた。ロボコンの父としても知られる森政弘博士(1927-)は早い時期に「軟体機械」と人工筋肉について論じている[森,1962]。
形状記憶合金アクチュエータについては、1980年代に軟体型マイクロマニピュレータの開発例がある[三輪,1986]。また、形状記憶アクチュエータのサーボ制御や[広瀬ら,1986]、能動内視鏡への応用が検討された[Ikuta et al.,1988]。
高分子アクチュエータについては、メカノケミカル反応を利用した軟体機械が構想され[多々良,1974]、ゲルアクチュエータによってハードウェアを「ウェットウェア」にしたソフトマシーン[長田ら,1994]が製作されるなど、柔らかいアクチュエータのロボット応用が進んだ[田所,1997]。圧電材料も、軟質な生物をモデルにした微小機械に利用された[林,1988]。
空気圧で駆動するソフトアクチュエータでは、1980年代に再びMcKibben型人工筋が取り上げられ、ブリヂストンが「ラバチュエータ」という名前で製品化し、筋駆動ロボットの研究が広がった[則次ら,1991]。繊維強化ソフトアクチュエータとしては、鈴森がフレキシブルマイクロアクチュエータ(FMA: flexible microactuator)[鈴森,1989]を発表した。
前ソフトロボティクス
1999年、日本ロボット学会誌でソフトロボティクス特集が組まれた。この特集で、ソフトロボティクスには、機構によるソフトネスだけでなく、現在のソフトロボティクスの対象にはなっていない制御によるソフトネスも加え、両方を包含したものをソフトロボティクスと名付けている[内山,1999]。ロボットをアクチュエータ、ジョイント、リンク、外装に分解して、それぞれにソフトネスを導入することを想定しており、それらが一体化した軟体ロボットはまだ意識されていないように思われる。
ソフトロボットに関連した初めての大型研究プロジェクトは、おそらく、日本学術振興会の未来開拓学術研究推進プログラムの「マイクロメカトロニクス・ソフトメカニクス」領域[岡村ら,2001]である。この領域で、1996(H8)年度〜2000(H13)年度の5年間、4つのプロジェクトが推進された。この領域の成果には、アメーバ状ロボット[嘉数ら,2001]、細径のMcKibben型であるマイクロ人工筋[下山,2001]、ジャミング現象を利用した機械拘束要素とソフトメカニカルスーツ[川村,2001]、脊椎をもつロボット[稲葉,2001]、やわらかい人工皮膚[篠田,2001]など、重要な研究プロジェクトが多数含まれている。また、軟らかい機械「軟生機械」の「形態機能」が論じられた[原,2001]。
新ソフトロボティクス
新興分野としてソフトロボティクスが広く認知され始めた2010年をソフトロボティクス元年と呼んでみたい。この年、日本では日本学術振興会(JSPS)の助成を受けて、スイス-日本交流事業セミナー「ソフトロボティクス:次世代ロボットのための形態機能の探究 」が開催された。
前節で述べたように、日本国内のソフトロボティクス関連研究の歴史は長いが、近年のソフトロボティクスについては北米とヨーロッパの研究グループが名付け、先導していると言わざるを得ない。その契機となったのはいくつかの大型プロジェクトである。
ひとつは、2008年〜2010年に実施された、MIT、ハーバード大学、iRobot社の参加するDARPAのChemBots (chemical robots)プログラムだった。この中では、アメーバのようなジャミング移動[Steltz et al.,2009]、ドラえもんハンドとして有名になったジャミンググリッパー[Brown et al.,2010]、もぞもぞ這うシリコーンゴム製の脚ロボット[Shepherd et al.,2011]、転がって走るイモムシロボット[Lin et al.,2011]、ソフト魚ロボット[Marchese et al.,2012]、形状記憶合金を使ったミミズロボット[Seok et al.,2013]などが開発された。シリコーン製のソフトグリッパー[Ilievski et al.,2011]などを開発しているハーバード大学のWhitesidesグループは、マイクロ流路を作るソフトリソグラフィーの技術で著名な研究室である。
もうひとつは、ヨーロッパで2009年〜2013年にEC(欧州委員会)の支援を受けて実施されたタコ規範型ロボットと身体性知能に関するプロジェクトOCTOPUSである。このプロジェクトで、やわらかい身体を計算資源として使うPhysical Reservoir Computingの研究を行ったのは中嶋浩平博士だ[Nakajima et al.,2013]。
関連コミュニティー
2010年代は組織化の動きが活発になり、2012年にはIEEE Robotics & Automation Society内にソフトロボティクスに関するTechnical Committeeが設立された。つづく2013年、EC(欧州委員会)の支援を受けてRoboSoft協会が発足している。2014年には初の学術専門誌Soft Roboticsが発行された。
筆者らは、日本国内でのソフトロボティクスの振興を目指して、2016年のロボット工学セミナー「やわらかいロボット、やわらかいデバイス」やその他のシンポジウムの企画開催を行なってきた。また、2017年4月から、日本ロボット学会ソフトロボティクス研究専門委員会を設立した。さらに、2018年には科研費の大型研究プロジェクト新学術領域「ソフトロボット学」が採択され、始動した。
この文章は、日本ロボット学会誌2019年37巻1号「ソフトロボティクス」特集号に掲載された解説論文「ソフトロボティクスはどこから来てどこへ行くのか」を加筆修正したものです。
文責:新山龍馬(ロボット博士)